箸は何本まで合法なのか問題 ~ご自由にお取りくださいという魔法~
■「お箸、何本入りますか?」という、現代の哲学的問い
「温めますか?」
「袋はご利用ですか?」
「……お箸、何本入りますか?」
この三連コンボ、社会人にとっては避けて通れぬ日常の儀式。
だが最後の問いには、哲学的な深みがある。
何本、入りますか?
いや、“膳”じゃない?
でも“本”って言われたし、指摘するのも野暮だし、私が今欲しいのは語彙じゃなくて栄養だ。
それに、二膳取ってしまったら“二人で食うつもりか”と見られそうで怖い。
「ひとつで……」
その一言に込められたのは、配慮、照れ、そして“人としてのライン”だった。
■では実際、何本までが「許容範囲」なのか?
紅生姜5袋
スプーン3本
ストロー2本
おしぼり4枚
ついでにレジ横の爪楊枝(20本くらい)
——これらを1回の買い物で持ち帰った場合、私はまだ「市民」なのか、それとも「初犯の窃盗犯」なのか?
■法律の視点で見てみる(※AIとの妄想会話です)
◇民法 第206条(所有権の内容)
所有者は、その物を使用し、収益し、処分する権利を有する。
→「ご自由にお取りください」と書かれているものは、その“自由”の幅が所有者のさじ加減にある。
◇刑法 第235条(窃盗罪)
他人の財物を不法に領得した者は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
→ 紅生姜を50袋持ち帰って冷凍保存していたら……“不法領得”と見なされる可能性があるというのか。
◇軽犯罪法 第1条?(不正持ち去り)
他人の物を無断で持ち去った者は、拘留又は科料に処する。
→ 「1人2つまで」と書いてあるのに7つ持ち帰った場合、該当の可能性は十分にあるのでは。
◇民法 第95条(錯誤)
表意者に錯誤があったときは、その意思表示は無効とする。
→ 「2本までと思っていた」「1本までしか提供していない」などの認識のずれにより契約が成立しない可能性も。
※これらはAIとの相談に基づく内容であり、実際の判断には個別事情が必要です。
法的な確証が必要な方は、弁護士など専門家へご相談を。
■別の解釈:その箸は、もはや“社会性”を試すリトマス紙
無料サービスとは、企業が我々の良心を信じて提供する“無言の契約”である。
つまり、コンビニのスプーンや箸は、
市民のモラルと人間性を測るテストキットなのだ。
「お箸、何膳ですか?」という問いに対し、
我々は何を返すのか。
「1つで」と答えるか、
「家族全員分で5本」と自信満々に言えるか。
すべては、己の社会的自尊心との闘いである。
■さらに拡張してみよう:ATMの封筒は“戦利品”なのか?
銀行のATMコーナーにある「ご自由にお使いください」封筒。
出張帰りの私は、つい「予備用に…」と3枚くらい持ち帰る。
小銭も入るし、レシートも挟める。実用的すぎる。
だが、何度か取っているうちに思う。
「これ……戦利品では?」
今日もまた私は、「銀行の紙袋に囲まれてる自分は善か悪か」を悶々と考える。
高騰するのは物価だけであってほしい(心の中のリミッターは据え置き)
最近は、弁当の値段も紅生姜の袋も、どこか「割高感」が増している。
一方で、無料で配られるものへの“貴重さ”も増している。
でも、それを“ごっそり”いってしまうと、心まで安くなる気がしてならない。
だから私は今日もこう言う。
「お箸、1つで」
だがその心の裏でこうも思っている。
(爪楊枝は3本までなら許されるよね……?)

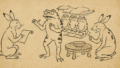

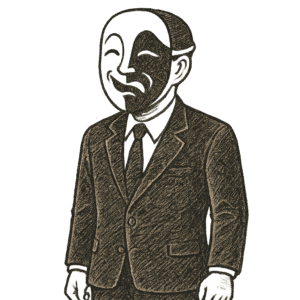
コメント