『幸せのちから』を観て、少し涙ぐんだ夜に
🍷はじめに(※ネタバレ注意)
※この記事には映画『幸せのちから(The Pursuit of Happyness)』のネタバレを含む感想と考察が含まれています。
まだご覧になっていない方は、ぜひ映画を観たあとに戻ってきてください。※ちなみに今回も、例によってお酒を飲みながら鑑賞していたため、記憶の曖昧な部分や感情的な解釈があるかもしれません。あしからずご容赦ください。
🎬 第1章:概要と前提(ネタバレなし)
本作『幸せのちから』(原題:The Pursuit of Happyness)は、実在の人物クリス・ガードナー氏の実話をもとに描かれた作品。
1980年代、シングルファーザーとして息子とともにホームレス生活をしながら、証券会社のブローカーになる夢を追った男の奮闘が描かれています。
タイトルにある「Pursuit of Happyness」の“Happyness”は、あえて綴りを間違えた言葉。それが示すのは、完璧ではないけれど、自分なりの幸福を追い求める人々のリアルな姿です。
劇中では、アメリカ独立宣言の一節「Life, Liberty and the pursuit of Happiness(生命、自由、そして幸福の追求)」に触れる場面があり、これは自然法思想にも関わる部分。
誰もが“幸福を求める権利”を持つ、という考え方が物語の根底に流れています。
なお、モデルとなったクリス・ガードナーさんは、現在は大成功した実業家として活躍しているとのこと。
🔍 第2章:ここからネタバレありで語ります
💭「意外と日常にチャンスはある」
映画を観て思ったのは、「チャンスは案外、日常の中に転がっている」ということ。
でもそれを掴むには、貪欲さと犠牲が必要だという現実も突きつけられます。
人は「安定」を欲しがります。今の生活を失うことへの恐怖が、動けなくする。
けれど、「今が最悪」ならば、むしろチャンスを掴みにいくべきではないか?
この映画は、そんな強いメッセージを静かに、でも真っすぐに投げかけてきます。
🧑💼 面接のシーン、わかる。ほんとにわかる。
面接のシーンでの“共感”は、特に強く感じました。
私自身、知り合いや関係者へ「この人をぜひ」と推薦した候補者が、
いざ面談の場にスーツを着てこなかったり、時間を勘違いしたりしていたことがある。
あのときほど、「なんでだよ……」と絶望したことはない。
信じて推薦した自分を責めるし、その人にも腹が立つ。
だからこそ、映画の中でボロボロの格好で必死に挑む主人公には、少し残念さもある。
まあ、私たちは“見ている側”だから事情を知っているけれど、
現実の面接では、一場面一場面が評価の材料になる。
だからこそ、信頼される人であれ、というメッセージにもつながってくるのかもしれません。
🚽 トイレのシーンと「どこで間違えたんだ」の問い
この映画には泣けるシーンがいくつかありますが、
私が一番心に来たのは、公衆トイレで一夜を過ごすシーンでした。
あそこはもう、「人としての尊厳ギリギリ」の場所。
子どもを守るために、自分が床で寝る父親の姿。
「どこで間違えたんだろう」
そんな気持ちが、静かににじみ出てくる。
でも、それでも前に進む。
それが“幸せを追う力”=“幸せのちから”なのかもしれません。
🏈 名刺配りと「嫌われていても売る力」
アメフト観戦で名刺を配ったとか、アメリカらしさを感じる行動ですね。
あれもまた一つの“戦略”です。
チャンスが流れている場所で、動くことの大切さが描かれています。
コネクションの重要性、どんなに嫌がられても挑む姿勢。
営業という仕事の泥臭さが、あまりにもリアルで、そして切実です。
🎉 ラストシーンと「幸福の定義」
そして、ラスト。
採用となった際に、主人公が外に出て、喜びをかみしめる涙ぐましいシーン。
カメラが引いていき、周囲にたくさんの人が映る。
この演出が秀逸でした。
「彼はついに“幸福の追求”を果たした」
……けれど、同じ道を歩いている人々にも、それぞれの苦労や物語があるのだと、無言で語っている。
つまり、あれは「彼だけが特別なのではなく、誰にでもチャンスはある」というメッセージでもあるのかもしれません。
🗝️ 第3章:締めくくりに
「チャンスは流れている。掴むかどうかは、自分次第。」
その一言に尽きる映画でした。(映画の名言ではないです)
何度も心が折れそうになっても、
子どもを守りながら、理不尽に耐えながら、それでも前を向く。
それが“幸福を追う力”=“幸せのちから”なのかもしれません。
▶️ 映画予告編(公式トレーラー)
次回はもう少し軽めの映画を予定していますが、
こういう“語りたくなる映画”に出会ったときは、
やっぱり黙っていられないのです。

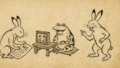
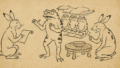
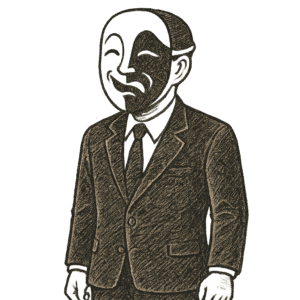
コメント