「日本語って、どれくらい話せればいいですか?」
国外にいる外国人の方とのオンライン面談。
「日本で働きたい」という真剣な気持ちが伝わってくる、前向きな印象の面談だった。
面談の本題が一通り終わったあと、私はこう伝えた。
「せっかくなので、何か質問があればどうぞ」――いわゆる“逆質問タイム”である。
すると彼は、少し迷ったあと、まっすぐに尋ねてきた。
「求めている日本語のレベルは、どれくらいですか?」
これは、採用面談では定番ながら、毎回悩ましい質問だ。
日本語レベルの“正解”って?
一般的には「日本語能力試験(JLPT)」というものがあり、
N1(最上級)からN5(初級)までのレベル分けがされている。
外国人採用の場合では、N3やN2を目安にしていることが多い。
「安心して任せられるレベルはN2くらいかな」といった声もよく聞く。
でも実際のところ、“その資格があっても通じない”ことは少なくない。
試験より難しい、現場の言葉
理由は簡単だ。
日本語学校では“標準語”しか教わらないのに、
実際に働く現場では“方言”が飛び交っている。
関西、東北、九州、どの地域にも独特のイントネーションと語彙がある。
しかも、それが“日常会話レベル”で使われる。
日本人ですら聞き返すような言葉を、外国人がすぐ理解するのは難しいのは当然だ。
教科書には載っていない現実
また、面接時に日本語が多少できていても、
実際の仕事現場では聞き取れなかったり、
「それ、学校では習っていません」と話がでることもある。
でもそれは、責められるようなことではない。
むしろ、受け入れる側が“現場の日本語”にどう触れてもらうかを工夫すべきだと思う。
私個人の回答:YouTubeで“生きた日本語”を
だから私は、こう答えた。(通じているのか、定かでない)
「正式な日本語の資格はあるに越したことはないけれど、
それ以上に大事なのは、日常の言葉に触れておくことです。
日本に来る前に“日本語のYouTube”をたくさん見てください。」
アニメでも、バラエティでも、街録インタビューでもいい。
とにかく、“いろんな日本語”を耳に入れておいてほしい。
「こういう場面では、こう返すのか」
「今の言葉、なんて意味だろう」
そんな引っかかりが、きっと力になる。
そして、こう続けた。
「あとね、日本では“聞き取れたこと”と“笑顔で返せること”、この2つが大事なんですよ。」
彼は少し驚いた顔で笑って、
「わかりました!」と、元気よく返してくれた。
その瞬間、すでに言葉の壁は一段、越えられていた気がした。
和歌でひとこと
試験より 動画に宿る 生き言葉
方言まじりで 笑うも勝ちよ
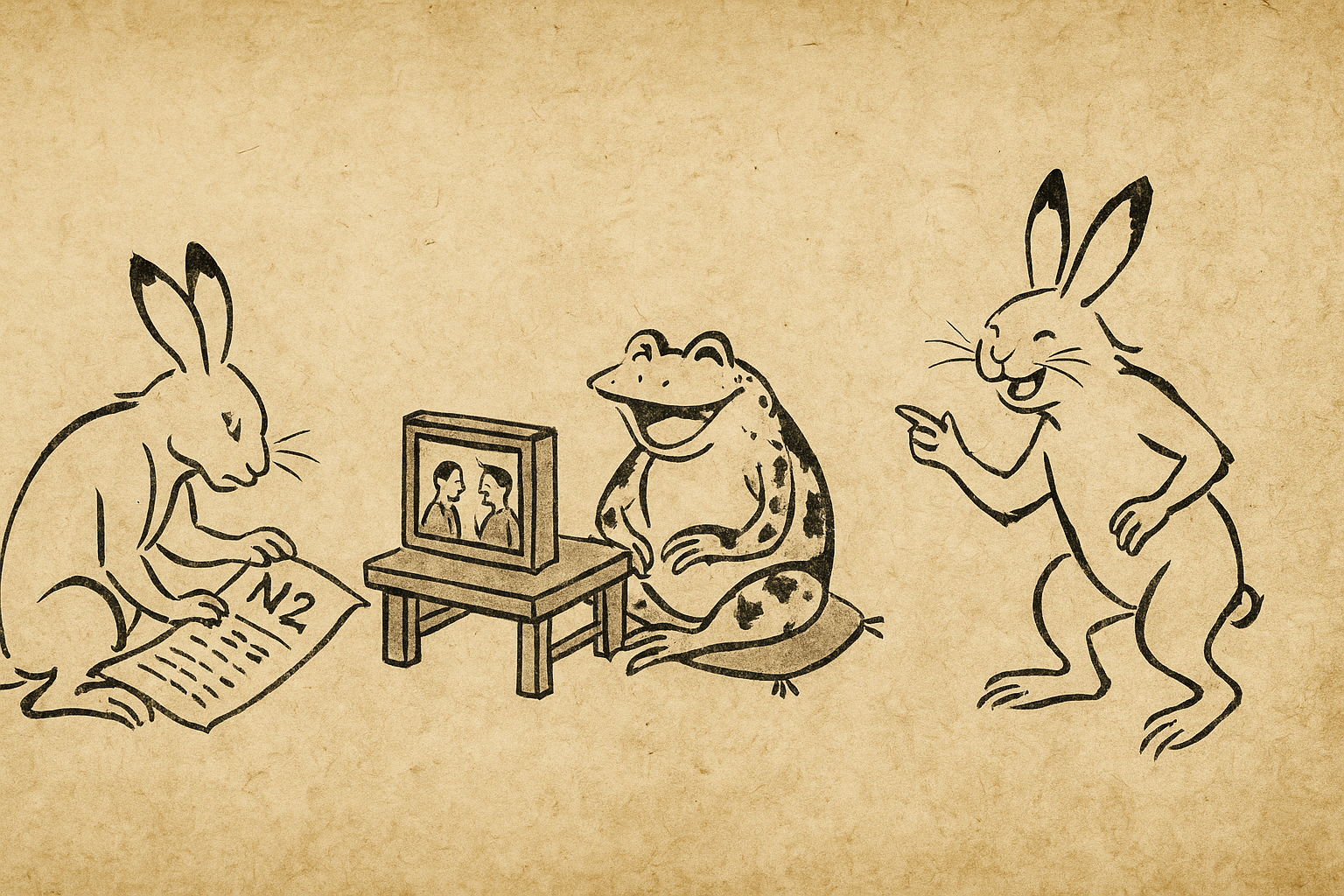
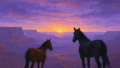

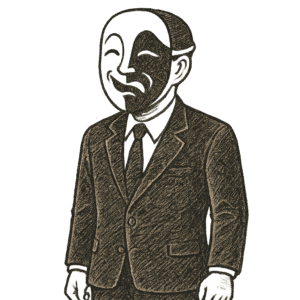
コメント